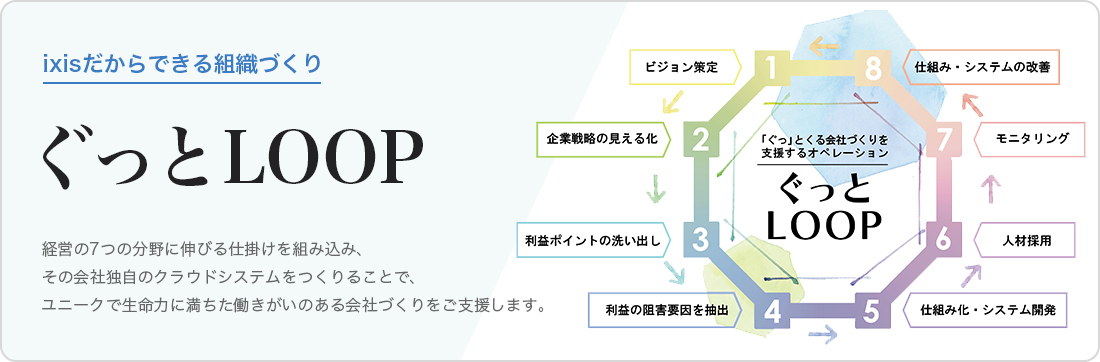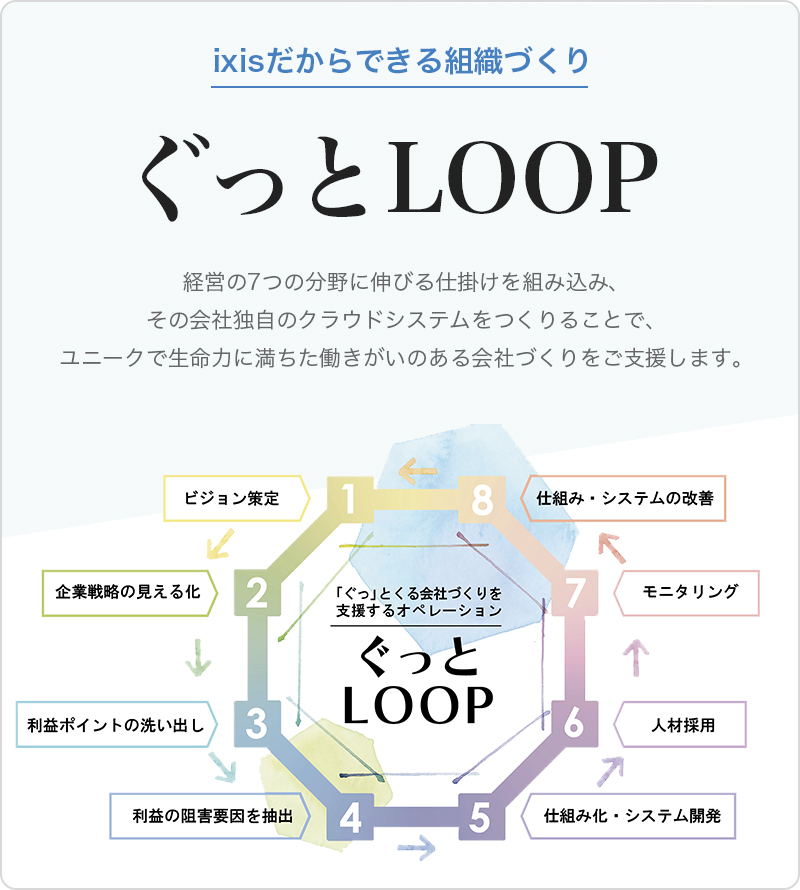- Shuhei Nakaso
続・kintoneとGemini連携!プロンプト改善でAIを“優秀なアシスタント”に育てる方法
続・kintoneとGemini連携!プロンプト改善でAIを“優秀なアシスタント”に育てる方法
前回の記事では、kintoneとGoogleのAI「Gemini」を連携させ、日報の自動要約を行う仕組みをご紹介し、社内外で多くの反響をいただきました。予告していた通り、今回はその続編です。前回構築した仕組みの“心臓部”である「プロンプト」に焦点を当て、ほんの少し工夫を加えるだけで、AIの回答の質を劇的に向上させるテクニックを深掘りしていきます。
AIは魔法の箱ではありません。AIは、「優れた指示に、優れた結果で応えてくれるツール」です。つまり、私たちがAIに与える「指示=プロンプト」の質が、そのままアウトプットの質に直結します。
この記事では、前回の基本的なプロンプトをベースに、3つの改善パターンを適用。実際に同じデータを入力し、出力結果がどのように変化するのかを比較実験します。この記事を読み終える頃には、AIを単なる「要約マシン」から、あなたの意図を深く理解する「優秀なアシスタント」へと育てるための具体的なヒントが手に入っているはずです。
プロンプト改善の比較実験
今回の実験では、前回も使用した以下の「次回勤務日の予定」を共通の入力データとして使用します。
【共通入力データ】
パターン0:ベースライン(前回のプロンプト)
まずは比較の基準となる、前回の記事で紹介した基本的なプロンプトとその出力結果です。
【プロンプト】
【出力結果】
- 要約: 次回の勤務では、IX社の新機能UIデザイン(3時間)、AI社のLPコピーライティング(2時間)、DC社のサーバー移行テスト(4時間)を担当します。IX社ではTOPページのファーストビューデザインが重要で、AI社では30代ITマネージャー向けのLPコピーを作成します。DC社では深夜にサーバー移行テストを実施します。合計9時間の作業を予定しています。
- 懸念点: IX社の新機能UIデザインにおいて、参考資料が不足しており、デザインの方向性が固まらない可能性があります。DC社のサーバー移行テストは深夜帯の作業となるため、予期せぬトラブル発生時のエスカレーションルートを再確認する必要があります。
このままでも十分に機能しますが、要約がやや淡白で、懸念点も事実を抜き出しているだけ、という印象です。ここから、AIの能力をさらに引き出していきましょう。
改善パターン1:「役割」を与えて、視点を変える
AIに特定の専門家としての「役割(ペルソナ)」を与えることは、最も簡単で効果的な改善手法の一つです。今回は「優秀なプロジェクトマネージャー」という役割を与えてみましょう。
【改善プロンプト】
【出力結果】
- 要約: 次回の勤務では、合計9時間の作業が予定されています。IX社では新機能UIデザイン案の作成(3h)、AI社ではLPコピーライティング(2h)、DC社ではサーバー移行テスト(4h)を行います。UIデザイン案はクライアント定例に向けた重要なタスクです。サーバー移行テストは深夜帯に行われます。
- 懸念点: IX社の新機能UIデザイン案作成において、参考資料不足による方向性の不明確さが懸念されます。DC社のサーバー移行テストは深夜作業となるため、予期せぬトラブル発生時のエスカレーションルート確認が必要です。
【比較と考察】
いかがでしょうか。単に事実を並べるだけでなく、プロジェクトマネージャーとしての視点が加わりました。「要約」にはタスクの重要性に関する示唆が含まれ、「懸念点」は単なる事実の列挙から、具体的なアクションを促す提言へと変化しています。このように役割を与えるだけで、AIはより文脈に即した、価値の高いアウトプットを生成するようになります。
改善パターン2:「思考プロセス」を指示し、アウトプットの質を高める
AIに複雑なタスクを依頼する場合、いきなり結論を出させるのではなく、人間と同じように「考え方(思考プロセス)」をステップ・バイ・ステップで指示すると、精度が格段に向上します。
【改善プロンプト】
【出力結果】
- 要約: 明日はIX社で新機能UIデザインに3時間、AI社でLPコピーライティングに2時間、DC社でサーバー移行テストに4時間の作業が予定されています。合計9時間の作業が割り当てられています。IX社のUIデザインでは、参考資料不足による方向性の遅延、DC社のサーバー移行テストでは、深夜作業における予期せぬトラブル発生時の対応が懸念されます。
- 懸念点:IX社【レベル:中】
- 【リスク:参考資料不足によるUIデザインの方向性遅延】
- 【対応策:事前に利用可能な参考資料をチーム内で共有し、不足している場合はクライアントへの確認を早めに行う。デザイン案の初期段階でフィードバックを求め、方向性のずれを最小限に抑える。】
- DC社【レベル:中】
- 【リスク:深夜作業における予期せぬトラブル発生時の対応遅延】
- 【対応策:事前にエスカレーションルートを再確認し、関係者の連絡先をすぐに確認できるようにしておく。テスト開始前に、想定されるトラブルと対応策を洗い出し、チーム内で共有する。】
【比較と考察】 思考プロセスを指示したことで、AIは単に懸念を抜き出すだけでなく、リスクの評価(高・中)と、それに対する具体的な対策案まで踏み込んで提案するようになりました。これは、管理職が次に行うべきアクションを直接的にサポートする、非常に価値のある情報です。複雑な指示も、このように分解して順序立ててお願いすることで、AIはその能力を最大限に発揮します。
プロンプト作成の3つのコツ
今回の実験から分かるように、プロンプトの改善はAI活用の効果を飛躍的に高めます。最後に、今日から使えるプロンプト作成のコツを3つご紹介します。
- 具体的であれ: 「いい感じに要約して」ではなく、「誰が、何のために、どのような形式で」必要なのかを具体的に伝えましょう。
- 役割を与えよ: AIに「広報担当者」「データアナリスト」といった役割を与えることで、その専門家の視点から回答を生成させることができます。
- 試行錯誤を恐れるな: 最高のプロンプトは、一度では完成しません。AIとの対話を通じて、少しずつ指示を調整し、あなたにとっての「最高の相棒」に育てていくプロセスそのものを楽しんでください。
まとめ:AIは、あなたの言葉で進化する
今回は、プロンプトを少し改善するだけで、AIの出力が劇的に変化する様子を具体的な事例と共にご紹介しました。kintoneとGeminiの連携は、単なる業務の自動化に留まりません。プロンプトという「対話」を通じて、AIをあなたのビジネスにとって最適なパートナーへとカスタマイズしていく、創造的なプロセスなのです。
私たちは、このような実践的なノウハウを今後も発信していきます。この記事が、皆様のAI活用をさらに一歩前進させるきっかけとなれば幸いです。