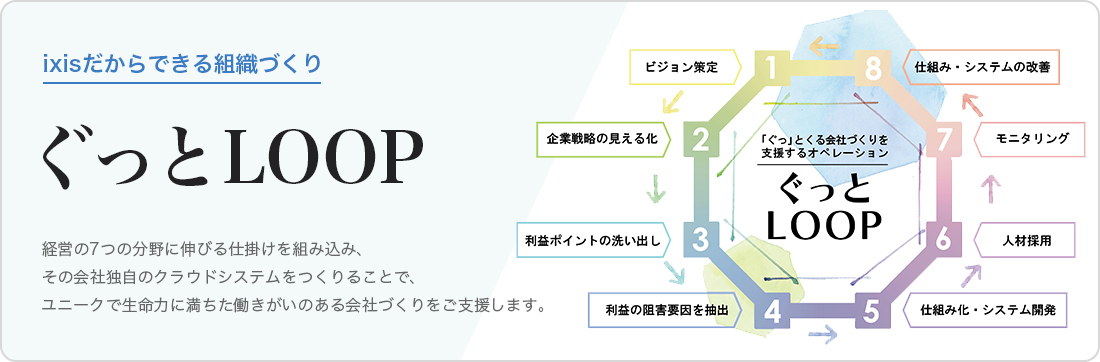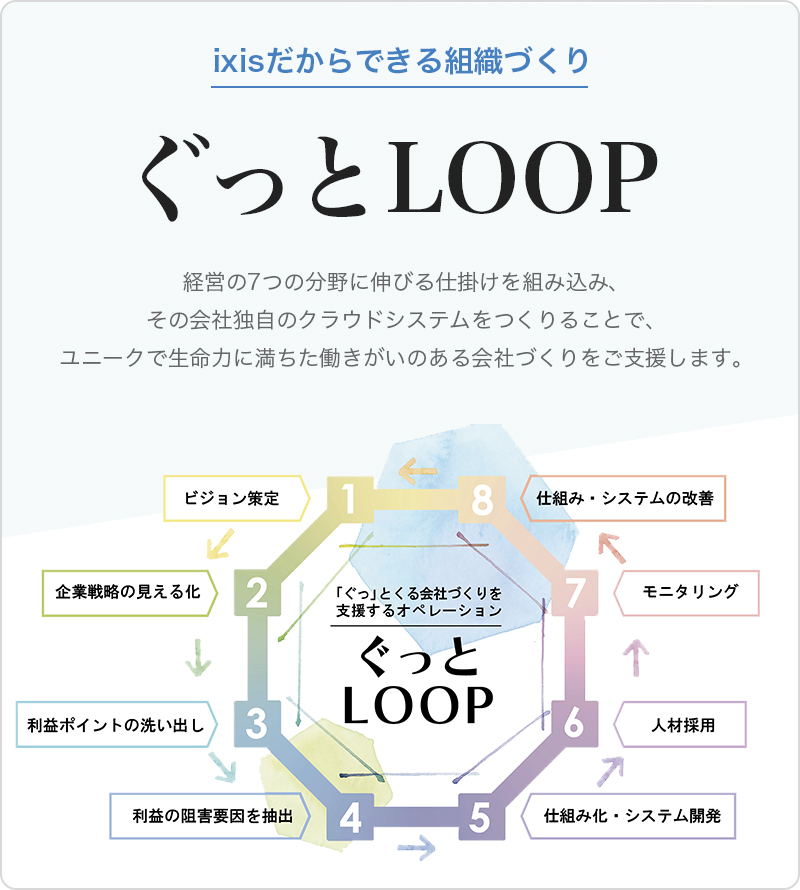- 杉原 里志
目的は地図にすぎない。登り方という物語が人を動かす
——そして、物語をつなぐ力と統治のバランスについて
組織のなかで、こんな場面を見たことがあるでしょう。
「このやり方でいきましょう」
「いや、それは非効率だ。こちらのほうが正しい」
目指しているゴールは同じはずなのに、いや、同じ“つもり”なのに、手段をめぐって激しい対立が起こる。
この光景は、多くの会社で繰り返されています。
なぜ人は、これほどまでに「登り方」にこだわるのでしょうか。
■ 手段は「自分の物語」である
人が手段に固執するのは、単なる方法論への執着ではありません。
その背後には「自分のこれまでの物語」があるからです。
営業一筋20年の人が「顧客の顔を見ずに売れるなんて信じられない」と言う。
現場叩き上げの人が「そんな計画は机上の空論だ」と言う。
そこにあるのは「自分のやり方で積み重ねてきた誇りを否定されたくない」という思いです。
手段とは成果を出すための方法である以上に、自分の人生を肯定する証なのです。
だからこそ、人は手段を否定されると、自分の存在そのものを否定されたように感じます。
■ 目的だけでは、人は動かない
多くのリーダーは「目的を共有すれば一致団結できる」と考えます。
「売上を伸ばそう」「顧客満足を高めよう」「新規事業を成功させよう」。
確かに目的は必要です。
しかし、人は同じ目的だけでは動けません。
「登る山が同じ」だけでは不十分なのです。
人が本当に心を燃やすのは「その山をどう登るか」という道筋。
そしてその道筋は、物語として語られるときに力を持ちます。
人は「自分が主人公として輝ける物語」でしか、本気になれないのです。
■ 物語がつながると、組織は豊かになる
営業は「顧客の信頼を築く物語」を描き、
現場は「努力が価値に変わる物語」を描き、
経営は「未来を守る物語」を描く。
これらを言葉で可視化し、つなぎ合わせれば、手段の違いは“対立”ではなく“創造”に変わります。
物語は違っていていい。違うからこそ立体的に進化できる。
これが、物語をつなぐ力の本質です。
■ しかし——物語の横行が生む「わがまま組織」
ところが。
「物語を大事にしよう」という考え方には、落とし穴もあります。
一人ひとりの物語が尊重されるあまり、組織が「わがままの集合体」になることです。
営業の物語、現場の物語、開発の物語。
それぞれが「自分の物語こそ正しい」と主張し合う。
するとどうなるか。
・会議は意見の洪水になり、収束しない。
・責任をとらずに「自分のやり方」にこだわる人が増える。
・組織全体としての速度が失われる。
つまり「物語がつながる」どころか、「物語が乱立して空中分解する」状態になるのです。
■ 主人公とわがままは紙一重
なぜそうなるのか。
それは「主人公感」と「わがまま」が、じつは紙一重だからです。
「自分の物語を生きる」という姿勢は、美しい。
しかし裏返せば「自分の都合だけを優先する」態度にもなり得ます。
自分が主人公であることは必要です。
ただし、同時に「他者もまた主人公である」という認識がなければ、それはわがままに転落します。
この境界線を守るものこそ、組織の「統治力」です。
■ 物語をつなぐには、ルールが要る
物語が尊重され、なおかつ統合されるためには、二つの力が必要です。
-
言葉の力 —— 目的を明確にし、物語を共有し、互いの違いを認める力。
-
統治の力 —— 組織としての優先順位を決め、収束させ、責任を明確にする力。
言葉だけでは理想論に終わります。
統治だけでは窮屈な官僚主義になります。
この二つのバランスこそが、物語をつなぐ組織に必要なのです。
■ 組織の「物語編集者」としてのリーダー
リーダーの役割は、全員を同じ物語に従わせることではありません。
一人ひとりの物語を「編集」して、一冊の本にまとめあげることです。
編集とは、取捨選択とバランスの作業です。
すべてのわがままを載せることはできません。
しかし切り捨てるだけでは、人は物語を語る意欲を失います。
だからリーダーには「言葉でつなぐ力」と「統治で収束させる力」の両方が求められるのです。
■ 統治の具体的方法
では具体的に、どのように統治すればよいのでしょうか。
-
ルールの明文化
物語を尊重しながらも、行動の最低基準はルールで定める。
「自由に語っていいが、最終決定には従う」「顧客情報は必ず共有する」など。
ルールは制約ではなく、共存の土台です。 -
責任の明確化
誰がどこまで責任を負うのかを言葉にして共有する。
責任が曖昧だと、物語は自由の名を借りた無責任に堕落する。 -
議論の仕組み化
議論は「勝ち負け」ではなく「統合」のために行う。
そのためには、ファシリテーションや合意形成のルールが不可欠。
「主張は数字か事例で裏づける」「批判だけでなく代案を示す」など。 -
優先順位の提示
物語を尊重しても、最終的には優先順位が必要です。
「今期は売上を優先する」「今回は品質を優先する」など、リーダーが旗を立てる。
このように統治があるからこそ、物語は無秩序なわがままにならず、組織の力として結集します。
■ バランスなき組織は二極化する
もし言葉ばかりで統治がなければ、組織は「わがまま横行の協調不全」に陥る。
逆に、統治ばかりで言葉がなければ、組織は「従属と沈黙の官僚機構」に落ちる。
前者はカオス、後者は停滞。
どちらも未来を切り拓くことはできません。
必要なのは、物語を尊重しながらも、組織の力を一点に収束させるバランスです。
■ まとめ——物語と統治のあいだに未来がある
人は目的だけでは動かない。
心を燃やすのは「登り方という物語」であり、「自分が主人公である実感」です。
しかし、物語の尊重が行き過ぎれば、わがままが横行し、組織はバラバラになる。
だからこそ、言葉による共有と、ルールによる統治が必要です。
リーダーは、物語を抑圧するのでもなく、放置するのでもなく、
「編集し、つなぎ、統治する存在」でなければなりません。
目的は地図にすぎない。
人を動かすのは、登り方という物語である。
そしてその物語がわがままに転じないようにするのが、統治の知恵である。
組織の未来は、この「物語」と「統治」のバランスの上に立っているのです。